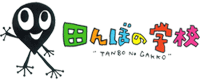第10回「田んぼの学校」企画コンテスト 開催要領

3つの部門に分けて表彰・支援します。
企画(立ち上げ)部門 / ステップアップ部門 / 連携プロジェクト部門【主催(応募・問合せ先)】
社団法人 地域環資源センター(「田んぼの学校」支援センター)
〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町11-8 フジスタービル2F
TEL:03-5645-3671 / FAX:03-5645-3675 / E-mail:tanbogk@acres.jp
趣旨
水田や水路、ため池、里山などを遊びと学びの場として活用し、環境に対する豊かな感性と見識を持つ人を育てる「田んぼの学校」活動を推進するため、優れた企画を表彰・支援します。
また、表彰・支援した企画の活動事例を広く紹介することにより、「田んぼの学校」活動の普及・活性化を図ります。
対象となるグループ・企画
3つの部門に分けて、表彰・支援します。部門ごとに対象となるグループ・企画が異なりますので、ご注意下さい。
部 門 |
対象となるグループ |
対象となる企画 |
| 企画(立ち上げ)部門 | 構成員に18歳以上の者を3名以上含むグループで、「田んぼの学校」企画コンテストでの受賞歴がないこと | 「田んぼの学校」としての新たな企画
※グループとしての活動実績は問いません。 |
| ステップアップ部門 | 構成員に18歳以上の者を3名以上含むグループで、「田んぼの学校」活動の実績があること | これまで取り組んできた「田んぼの学校」活動を発展(ステップアップ)させる企画 |
| 連携プロジェクト部門 | 構成員に18歳以上の者を3名以上含むグループ、3つ以上の連携体 | 「田んぼの学校」活動を広げたり、深めたりするために複数のグループが共同で取り組む企画 |
※「連携プロジェクト部門」は、複数のグループの連携による「田んぼの学校」の実践だけでなく、「田んぼの学校」を推進するための各種活動の企画も対象となります。
応募方法
所定の応募用紙に必要事項を記入し、郵送またはEメールにて応募してください。(FAX不可)
企画(立ち上げ)部門 応募用紙[WORD版] |
ステップアップ部門 応募用紙[WORD版] |
連携プロジェクト部門 応募用紙[WORD版] |
※Eメールでの応募の際は、見出しに「田んぼの学校 企画コンテスト応募」と入力してください。
※応募時に提出された資料は返却いたしません。
応募期間
平成20年2月25日(月)〜平成20年4月11日(金) ※募集は終了しました。
賞
○企画(立ち上げ)部門…企画賞 10点程度○ステップアップ部門…優秀賞 5点程度
○連携プロジェクト部門…優秀賞 5点程度
※入賞グループには、所定の様式による活動報告書の提出および「田んぼの学校」企画コンテスト報告会における活動報告を義務づけます。
選考
いずれの部門も以下の選考委員により行います。【選考委員】
守山 弘(東京農業大学客員教授)※委員長阿部 治(立教大学大学院異文化コミュニケーション研究科教授)
大串 和紀((社)地域環資源センター専務理事)
選考基準は次のとおりです。
(1)選考基準(全部門共通)
ア.農業・農村の多面的機能を活用した企画であること。イ.環境に対する豊かな感性と見識を持つ人を育てることにつながる企画であること。
ウ.計画に具体性があり、実行可能なこと。 なお、支援の効果についても勘案します。
(2)部門ごとの審査の視点
※以下のすべてをバランスよく満たさなくてはいけないということではありません。
○企画(立ち上げ)部門
a.グループや企画内容の独自性、独創性(特に企画内容については農業・農村への多様なアプローチを評価)
b.地域活性化、農業振興とのつながり
c.地域の自然および文化の保全・再生とのつながり
d.多様な主体のかかわり
○ステップアップ部門
企画部門a〜dの項目に加え、e.活動や活動主体の継続性と発展性
○連携プロジェクト部門
a.連携による成果(「田んぼの学校」の広がりや深まり)の見通しb.連携による波及効果(他分野との交流促進、地域への貢献等)
発表
入賞グループに直接通知します(平成20年4月下旬を予定)。本コンテストに関する情報の取扱いについて

本コンテストへの応募により得た情報を、応募グループの了承なく、第3者に提供したり公開することはありません。また、個人情報の取り扱いには十分に配慮します。
連携プロジェクト部門について
「連携プロジェクト部門」は、複数のグループの連携による「田んぼの学校」の実践だけでなく、「田んぼの学校」を推進するための以下のような活動の企画も対象となります!
ネットワークづくり、普及・推進のためのイベント開催
地域全体として「田んぼの学校」活動をより活性化させるため、一定の地域内で「田んぼの学校」に取り組んでいるグループが情報共有できるしくみをつくる。また、共同イベントを実施する。
具体例
○○県全体として「田んぼの学校」活動を盛り上げていくため、○○県「田んぼの学校」ネットワークを立ち上げ、○○県の地域性を活かした「田んぼの学校」の活発な展開、特に学校教育との連携に向けて議論するフォーラムを開催する。勉強会
自分たちの取り組んでいる活動を深めたり、新たな分野への取組みを広げたりするため、関連分野の取組みを行っているグループと学び合いの機会を設ける。
具体例
子どもの体験活動をメインとした「田んぼの学校」を実施してきたが、環境保全型農業に取り組んでいる農業者と連携して、農業と環境を考える大人の「田んぼの学校」を計画中。同様の取組みを行っているグループと連携して、環境保全型農業についての勉強会を開催し、今後の活動企画に活かす。プログラムづくり
他の「田んぼの学校」実践グループと情報交換をしながら、目的をより効果的に達成できるプログラムづくりに取り組む。
具体例
これまで農作業体験を中心とするプログラムを実施してきたが、今後田んぼの生きものにふれあうプログラムも実施していくことを計画中。生物の専門家やすでにこのようなプログラムに取り組んでいるグループと連携して、農業と生きものとのかかわりを楽しく学べるプログラムをつくる。上の例にかぎらず、みなさんの「田んぼの学校」の実践を踏まえ、どんどんアイデアを出してください。
これまでの受賞団体の情報はこちらで紹介しています。